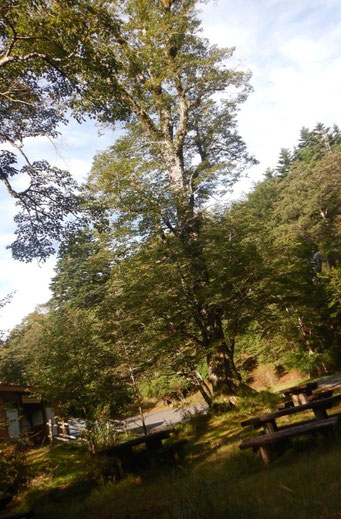- ホーム
- 日々のこと
- 同居人のこと
- 歩いてみれば好日
- 25年7月~8月
- 25年5月~6月
- 25年4月~5月
- 24年12月~25年4月
- 24年9月~12月
- 24年7月~9月
- 24年4月~7月
- 24年3月~4月
- 23年11月~24年3月
- 23年9月~11月
- 23年6月~9月
- 23年4月~6月
- 23年4月
- 23年2月~3月
- 22年10月〜23年2月
- 22年8月〜10月
- 22年5月〜8月
- 22年2月〜5月
- 21年10月〜22年1月
- 21年8月〜10月
- 21年5月〜8月
- 21年3月〜5月
- 21年1月〜3月
- 20年9月〜12月
- 20年5月〜9月
- 20年3月〜5月
- 19年10月〜20年2月
- 19年8月〜10月
- 19年6月〜7月
- 19年3月〜5月
- 18年12月〜19年3月
- 18年10月〜11月
- 18年8月〜9月
- 18年5月18日〜7月
- 18年4月〜18年5月17日
- 17年12月〜18年3月
- 17年11月
- 17年9月〜10月
- 17年7月〜8月
- 17年5月〜6月
- 17年3月〜4月
- 16年12月〜17年2月
- 16年11月
- 16年10月
- 16年9月
- 16年8月
- 16年6月・7月
- 16年5月
- 16年3月・4月
- 16年1月・2月
- 15年11月・12月
- 15年10月
- 15年9月
- 15年7月・8月
- 15年6月
- フォトギャラリー
- 染織のこと
- わたしの「う」
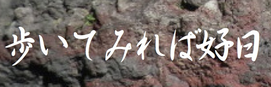
日本列島は、4つの大きなプレートがせめぎ合うちょうど上にあります。災害列島たる所以でもあります。
4つのうち、唯一フィリピン海プレート上にあるのが伊豆半島です。 およそ2000万年前の太平洋上の小さな火山島が、フィリピン海プレートに乗って北上し、本州に衝突して出来上がった伊豆半島。
なんだかまるで「ひょっこりひょうたん島」のようで、想像を搔き立ててくれます。 そして今なお、北へと本州を押し上げつつあります。
そんな伊豆に暮すようになってから、ずいぶんと月日が経ちました。 成り立ちの面白さ、独特の地層や伊豆半島固有の植物たち。
歩いて、歩いて、伊豆の自慢をしたいと思います。
●歩き始めた詳しいいきさつは→こちらをどうぞ

●●●お願い●●●
植物は類似した種が多く、
●メールでのご連絡先→ ori@ohnojunko.com
★★ 写真をクリックすると拡大写真が見られます。★★
本日の狙い、ムキタケです。晩秋に出始めるキノコで、ツルリ・トロリとした触感で、私はコンソメでシンプルなスープにするのが好きです。よく汁気を吸うので、すき焼きに入れたりしてもとても美味しいです。
狙いどおり、カゴいっぱいにムキタケを収穫して、大満足です。ムキタケが出始めると、キノコ・シーズンもそろそろ終わり。
10月も半ばを過ぎてなお、富士山に初冠雪の便りはありませんが、森は美しく色づき始めて、あとしばらくしたらこの辺りも雪に閉ざされることになりそうです。
富士山麓でのキノコ採りも今日が最終日となりそうです。また来年。早くも待ち遠しくなりました

10月8日(水)今日のキノコ
5日前、ナラタケ・ツリーにウスヒラタケ・タワーを満喫しましたが、さて本日はどうなっているでしょうか。
ナラタケはすでに最盛期を過ぎ、成菌から老菌になりかかっている状態のものが多く、湧き出るように這い上る木々が見飽きるほどありました。

一口にナラタケといっても、最近ではいくつかに細分化が進んだようです。ナラタケ(広義)の基本的な特徴は同じですが、地域によってずいぶん違いがあるのを実感しています。
その中で、これは初めて見るナラタケ。全体的に黒っぽくてクロゲナラタケでしょうか。黒っぽい=クロゲナラタケという単純な帰結はよくありませんが。
木の洞に守られるようにしてヌメリスギタケの一束。
ヌメリスギタケ、ヌメリスギタケモドキ、スギタケ、ツチスギタケ、スギタケモドキとよく似た見た目のキノコがたくさんあります。このうち、ヌメリスギタケとヌメリスギタケモドキは、まあ安心して食べられると思っています。他は人によっては中毒を起したり、本によっては有毒とされているので、手を出さない方が賢明です。
ヌメリスギタケとヌメリスギタケモドキはカサの鱗片の違いで見分けています。ヌメリスギタケはカサも柄もぬめると言いますが、乾燥しているとよくわかりません。規則的で端正な感じの鱗片がヌメリスギタケでしょうか。
そろそろ、晩秋のキノコが出始める季節になってきました。まだまだ、しばらくキノコに遊んでもらいます。
10月3日(金)秋のキノコ
富士宮口五合目まで登ってきました。夏山シーズンの終わった富士山はすっかり静かで、近くを散策する人や山小屋や道路の冬支度をする人たちがパラパラいる程度です。
私と友人は五合目から少し下りながらハナイグチを中心に探します。
9月25日(木)村山古道
山友を誘って、キノコ偵察を兼ね、村山古道を歩きました。ようやく猛暑がおさまってきて、朝晩は少し冷えるようになりました。
わずかに残る古道の痕跡を辿りながら、五合目から六合目へと昇ってきました。
少し霞んではいるものの、晴天。弧を描く宝永火口は見飽きぬ美しさです。標高2500m、一桁台の気温かと思ってダウンジャケットを持ってきましたが、まるで真夏のような暑さでした。
9月18日(木)まだまだ猛暑

いったいいつになったら秋は来るやら。標高2000m、例年の今頃なら、朝は一枚羽織りたくなるくらいの気温ですが、今日は半袖でも暑いくらいです。
気温が下がらねば地面の温度も下がらず、キノコは地上に出てきません。

菌果薄い本日のキノコは、ハナイグチ、キノボリイグチ、アミハナイグチ、ススケヤマドリタケ、オオキノボリイグチ、ヤマドリタケ、シロヌメリイグチ、ヤマイグチ等、イグチの仲間。
ホウキタケ、コウタケ、クロカワ、ツガタケ、オオツガタケ、ホンシメジ、ショウゲンジ、カワムラフウセンタケ、ヌメリササタケは少しだけ。 オニナラタケもポツリポツリ。こうして列挙してみれば、富士山の裾野のキノコの種類の豊かさは格別です。
雨と秋を待ち望むばかりの本日の菌行でした。
9月11日(木)秋の植物観察
明け方、猛烈な雷雨でしたが、予報では日中はまずまず。思い切って花友と出かけてきました。予報以上に良い天気になりました。

久しぶりの雨でしっとりした林間の道は気持ちよく、東光寺の手前ではひとつ、ふたつヒガンバナが咲き始めていました。
まれに見る猛暑といえど、花は宇宙の中で我を失わず季節を違えませんね。右往左往しているのは人間だけです。

沢沿いに湯河原道を下って、何年かぶりで見に来ました。
数年前には、川べりに一面に広がる花が見事でしたが、その後の台風の土石でかなりダメージを受けたようで、花芽を付けるほどに成熟した株はほとんど見られないのが残念でした。
小さな株はたくさん残っていましたので、あと数年後の再生を待ちたいと思います。

登り返して岩戸山までやってきました。初めてだという同行者と、せっかくなので岩戸観音まで下りてみました。
岩戸山まで来たのはチャボホトトギスを見つけたかったからですが、残念ながら出会うことができませんでした。
林床の花たち。見かけたツルリンドウは全て白花でした。意外に珍しい。
草原まで戻ってきました。ススキの穂が一面に揺れる南斜面が美しい。
秋の花々、今年も変わらない顔ぶれにほっとしています。


9月9日(火)キノコの王様
今日撮った写真はこの1枚のみ。型は最高、ズシリと重く、だれもかれも大喜びをしたのは言うまでもありません。
このくらいの蕾ですと、ほとんどマツタケの匂いはしませんが、持って歩くと少しずつ開くのか、匂いがしてくるのが普通ですが、今一つ香りに乏しい。
キノコ師匠に持ち帰ってもらって、じっくり鑑定をしてもらったところ、どうやらニセマツタケらしい!マツタケと間違えて売られていることもあるようなので、素人にはどうにも鑑定はできません。
残念ではありましたが、楽しませてもらいました。
9月3日(水)キノコシーズン開始
富士山五合目須走口、毎年シーズンの幕開けはここで始まります。相変わらず続く猛暑と雨なしであまり期待は持たずに、それでもやはり来たくてうずうずしていました。
行ったことがないという同行者のために、小富士に立ち寄りました。山頂に登る小さな人の姿まで見えるほど晴天で素晴らしい景色。
天城の山々、駿河灘、丹沢の山並み、南アルプスの山々も見えて爽快です。眼下の雲海は夏の積乱雲、空高くには刷毛ではいたような涼やかな秋の巻雲が広がっています。こんな夏から秋へと移り変わる空を「行き合いの空」というのだと、キノコ師匠が教えてくれました。